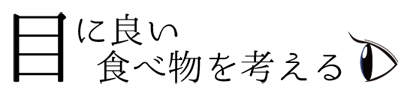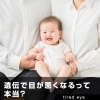眼精疲労の対策方法は?

目を酷使することが多い日常生活で、目の疲れがたまる時もあると思います。
目の疲れは、目を保護・休ませたり、身体を動かして血流をよくしたり、温めたり。大概、一晩休むと次の日にはスッキリと疲れが抜けます。
でも、中には疲れが抜けることなく、目が重い、痛みを感じる、乾く、しょぼしょぼする、けいれんする、充血する、かすむなどの他、頭痛、吐き気、首や肩のこり、めまいなどの症状がでることもあります。こういった、何らかの処置・対策を取らないと改善できない疲れが、「眼精疲労」と呼ばれています。
目の病気、からだの病気が隠れている場合もありますので、「おかしいな」と感じた方は、眼科へすぐに受診してください。
それでは、病気はない前提で、「眼精疲労」についての対策をレポートしていきます。
眼精疲労の原因を探る
目や頭痛・首や肩の痛みが出ている時点で、眼精疲労は辛いのですが、原因が掴めると改善が図れます。目を酷使して、近距離での作業や、長時間の作業、同じ姿勢での作業、暗いところでの作業をしていませんでしたか?
血流を意識する
身体を動かさなかった時間が長くなってしまったため、血流が悪く、眼球への血流も乱れ酸素不足が考えられます。作業が忙しくても30分~1時間おきに、首や肩を回す、肩甲骨を大きく動かす、ふくらはぎを動かす、つま先を上げ下げするなどして、身体をほぐしましょう。
お風呂でできる血流改善
また、お風呂に浸かっているときに、ふくらはぎを揉むこともおすすめします。「第2の心臓」と呼ばれるふくらはぎ。足から心臓へ、下から上へ血液を送らないといけないのですが、じっとしていることで、働きが弱まってしまいます。ですので、お風呂でゆったりお湯に浸かりながら、ふくらはぎを揉んで、血液を循環させてくださいね。
絶対におすすめ!ヘッドマッサージ
目を酷使して、緊張状態が続いていると、頭皮や頭も血行が悪く、頭皮が凝ってきます。シャンプーをしながら、頭皮をしっかり揉むと、硬かった頭皮が少しずつ柔らかくなってきて、洗い上りはスッキリ気分爽快です。頭蓋骨に沿って指を置き、頭皮を押し付けながら、挟むように動かします。だんだん頭皮が柔らかくなってきて、動くようになってきます。市販のシャンプーブラシでも気持ちいいですよ。部屋でもできますが、マッサージをしていると頭の脂のにおいが出てくるので、シャンプー時がおすすめです。

私は頭痛・首・肩が痛くなる時がありますが、シャンプー時のヘッドマッサージは頭痛にとっても効きます。しかも即効性があり、早く改善します。コチコチの頭皮を強く動かすので、最初は痛いのですが、いつもより長めに洗いながら、頭皮を揉みこみます。頭皮が動き始めてくると、徐々に柔らかくなってきて、痛みも減ってきます。
こどもたちにも、マッサージをすると「痛い!」と言われますが、スッキリするようです。今の小学生はタブレットやゲームの使用時間が多いですからね。。。
気になったパパにもリクエストされて、頭皮マッサージをやってあげたら、思ったより痛かったようで、抜け毛を気にされてしまいました(涙)
頭皮が柔らかくなれば改善できると思うので、少しずつほぐしていってみてくださいね。
布団で肩甲骨周りをほぐそう
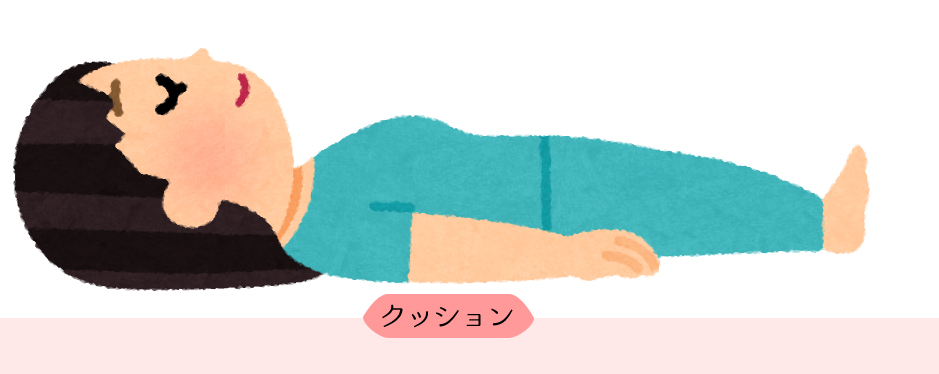
肩甲骨のあたりにクッションを置き、横になります。胸が開くように伸び、肩甲骨がとても気持ちいです。長時間の作業をしていると、姿勢も悪くなりやすく、肩が丸くなっていることがあります。胸をはって、ほぐしリラックスしましょう。
専用の商品も販売していますが、まずは自宅にある枕やクッションで試して、気持ちいいかどうか確認してみると良いと思います。
この肩甲骨を伸ばすストレッチをしていると、あまりの気持ちよさに寝落ちしてしまい、いつの日か寝違えるのでは?と心配になることがあります。試す皆様はどうか気を付けて、身体をほぐしてくださいね。
五行説より考える栄養 ~目の疲れは「肝」が弱っている~
中国には「五行説」という、自然の理を解く考え方があります。「木・火・土・金・水」の5種類の万物が、お互いに影響を与えたり、循環しているという思想です。
詳しい話は、検索サイトで調べると出てきますので、目に関連のある「木」について、大切なポイントに注目していきますね。
「木」は、五臓は肝、五官は目、五志は怒、五味は酸、五声は呼を示す
五臓は、肝臓、心臓、脾臓、肺臓、腎臓の五つの内臓を指すのですが、「木」の五臓である「肝」は「肝臓」だけでなく「自律神経」も象徴します。「肝」が弱ると病気が現れる場所(五官)は「目」で、不調になったときに怒りやすい、酸っぱいものを好む、怒鳴りやすいと考えられています。もちろん、必ずしも当てはまるわけではないのですが、参考になりますね。
目が疲れたなと感じる時は、肝臓に優しい食べ物や、酸っぱいお酢やレモンなどを積極的に摂りましょう。
肝臓に良い栄養は、ビタミンA、C、E、B1、B12です。うなぎ、レバー、ほうれん草、ブロッコリー、ごま、豚肉、ピーナッツ、カキ、卵。
肝臓の解毒能力を高めてくれるタウリンは、イカや貝類に多く含まれています。
傷ついた肝臓を修復してくれるタンパク質は、魚、肉、卵、大豆製品、乳製品で摂ることができます。
肝臓の負担になっているコレステロールの排出には、オメガ3脂肪酸と呼ばれるえごま油、しそ油、青魚の脂であるDHAとEPAです。なかなか摂りにくいオメガ3脂肪酸ではありますが、青魚では、マグロ・サンマ・サバがDHAとEPA共に多く含まれているようです。意識して摂取することをおすすめします。
自律神経にも影響し、不調のサインとして、怒りっぽくなっている・怒鳴りやすい傾向があるかもしれません。怒らないように、怒鳴らないようにすることで、改善が早くなるかもしれませんので、ゆっくりリラックスすることも忘れないでくださいね。
近距離での作業をお休みして、遠くの景色を眺めることもおすすめです。